しっくのん Q&A
「しっくのん」の特長は?
しっくのん&漆喰 比較表
| ||||
しっくのん
| 漆喰
| |||
主原料
| 消石灰+水
| 消石灰+水
| ||
性状
| スラリー
| 粉体
| ||
調合
| 既調合
| 現場調合
| ||
施工方法
| ローラー・刷毛
| コテ
| ||
施工面積(目安)
| 約2m2/㎏
| 約0.8m2/㎏
| ||
施工業者
| 主に塗装業者
| 主に左官業者
| ||
塗り重ね
| ○
| ×
| ||
不燃性
| ○
| ○
| ||
調湿性
| ○
| ○
| ||
ホルムアルデヒト発散等級
| 指定対象外
| 指定対象外
| ||
施工道具について
A3: 通常はホームセンターなどにある、高粘度塗料用「中毛13mm」が比較的塗り易いです。
凹凸の大きいクロスなどの下地の場合は、中毛のローラーで塗装をすると凹部分に塗料が入り込まずに、ムラに仕上がる場合があります。「長毛18mmか20mm」で塗装をすると凹部分に塗料が入り込みます。
凹凸の大きいクロスなどの下地の場合は、中毛のローラーで塗装をすると凹部分に塗料が入り込まずに、ムラに仕上がる場合があります。「長毛18mmか20mm」で塗装をすると凹部分に塗料が入り込みます。
塗料を入れる『バケット』には取っ手の付いたカゴのようなものがあります。
マスキングテープにも千切りやすいテープや写真のようなビニール付きのテープもあります。
使用後はすぐに水で洗浄して下さい。乾燥しますと塗料が取れにくくなります。
施工を中断する場合は、ローラーをラップで包んでおくと固まらずに済みます。
マスキングテープにも千切りやすいテープや写真のようなビニール付きのテープもあります。
使用後はすぐに水で洗浄して下さい。乾燥しますと塗料が取れにくくなります。
施工を中断する場合は、ローラーをラップで包んでおくと固まらずに済みます。
下地処理について
A4: 塗装の境界部分等はマスキングテープやマスカー(ビニール付養生テープ)、新聞紙等でマスキングして下さい。木部に塗料が付着すると、木の材質によっては変色する場合があります。
1. 石膏ボードのジョイント部は所定のピッチで、ネジまたは釘で胴縁にしっかりと固定して下さい。
2. ジョイント部には図1.のように必ず4~6㎜の大きめのテーパーを取って下さい。図2.のようなテーパーのないジョイントは避けて下さい。
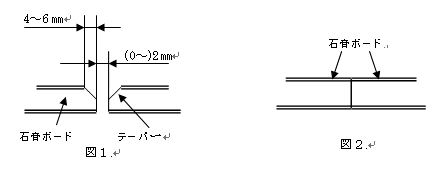
4. ジョイント部のパテは無機系の物を使用して下さい。樹脂系のパテは、塗膜の隠ぺい不足やクラック発生の原因となる場合がありますので、使用しないで下さい。
6. パテ部にヤセやクラックが発生していないことを確認し、グラインダーやサンドペーパー等で研磨して下さい。その際、図3.のように僅かにパテ厚を残して下さい。図4.のように研磨しすぎると、しっくのんを塗装した際、塗装ムラの原因となる場合があります。
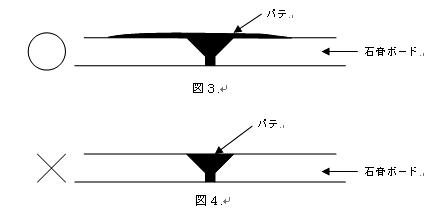
塗装面の汚れ(油分・手垢・ホコリなど)は、十分に落として下さい。
塗料が接着しにくくなったり、塗膜に浮き出てくる可能性があります。下地は十分に乾燥させて下さい。特に、冬場は下地が凍結している場合があり、そのまま施工すると接着不良を起こす恐れがありますので、施工前には凍結がないか確認してください。
塗料が接着しにくくなったり、塗膜に浮き出てくる可能性があります。下地は十分に乾燥させて下さい。特に、冬場は下地が凍結している場合があり、そのまま施工すると接着不良を起こす恐れがありますので、施工前には凍結がないか確認してください。
a)石膏ボード
石膏ボードのジョイント部は適切な処理を行わないと、塗装後にクラック発生の原因となります。
石膏ボードのジョイント部は適切な処理を行わないと、塗装後にクラック発生の原因となります。
1. 石膏ボードのジョイント部は所定のピッチで、ネジまたは釘で胴縁にしっかりと固定して下さい。
2. ジョイント部には図1.のように必ず4~6㎜の大きめのテーパーを取って下さい。図2.のようなテーパーのないジョイントは避けて下さい。
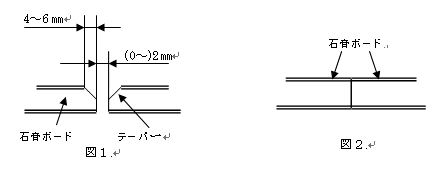
3. テーパーを取るとジョイント部に石膏面が露出します。石膏はパテとの接着性が非常に弱く、クラックの原因となります。石膏とパテとの接着性を高める為に、効果のあるシーラーを筆(もしくは刷毛)で塗って下さい。
4. ジョイント部のパテは無機系の物を使用して下さい。樹脂系のパテは、塗膜の隠ぺい不足やクラック発生の原因となる場合がありますので、使用しないで下さい。
※ パテの材質によってはしっくのんの塗膜にパテのアクが浮き出る場合があります。
懸念される場合は、アク止め処理を行って下さい。
※ 推奨パテ:宇部吉野石膏㈱製「タイガージョイントセメント ペーストタイプ」
懸念される場合は、アク止め処理を行って下さい。
※ 推奨パテ:宇部吉野石膏㈱製「タイガージョイントセメント ペーストタイプ」
5. パテは目地幅より広めに塗って下さい。
6. パテ部にヤセやクラックが発生していないことを確認し、グラインダーやサンドペーパー等で研磨して下さい。その際、図3.のように僅かにパテ厚を残して下さい。図4.のように研磨しすぎると、しっくのんを塗装した際、塗装ムラの原因となる場合があります。
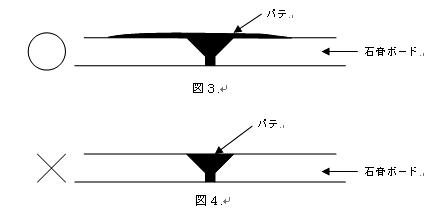
b)コンクリート及びモルタル
よく乾燥していることを確認して下さい。 エフロ、レイタンス、ゴミ、汚れ等はワイヤーブラシ、サンドペーパー等で除去して下さい。打継ぎの段差、目違い、異物の突起、セメントかす等はサンダーで平滑にして下さい。ピンホールやクラックがある場合は補修して下さい。
よく乾燥していることを確認して下さい。 エフロ、レイタンス、ゴミ、汚れ等はワイヤーブラシ、サンドペーパー等で除去して下さい。打継ぎの段差、目違い、異物の突起、セメントかす等はサンダーで平滑にして下さい。ピンホールやクラックがある場合は補修して下さい。
c)合成樹脂ペイント及びクロス
汚れをしっかりと落として下さい。特に油分、油膜があるとしっくのんの接着性が劣ります。タバコのヤニ等はしっくのんの塗膜に浮き出てくる可能性があります。その場合はアク止め処理を行って下さい。
汚れをしっかりと落として下さい。特に油分、油膜があるとしっくのんの接着性が劣ります。タバコのヤニ等はしっくのんの塗膜に浮き出てくる可能性があります。その場合はアク止め処理を行って下さい。
注意:合成樹脂ペイント及び塩化ビニルクロスにはしっくのんAは塗布できません。(クラックが入りやすくなります)
しっくのんの適用下地は?
A5:
石膏ボード、セメントモルタル、コンクリート、合成樹脂ペイント、ビニールクロスなど。
*合成樹脂ペイント、塩化ビニールクロス下地につきましては、種類や状態によっては塗布できないものもあります。(防水・撥水加工がしてあるものなど)
*クロスを剥がした上に塗装する場合は、必ずクロスの裏紙まで剥がして下さい。
裏紙が残ったまま塗装すると、下記写真のように裏紙の糊が膨れて塗膜を押し上げ、クラック・塗膜剥離を起こします。
*クロスを剥がした上に塗装する場合は、必ずクロスの裏紙まで剥がして下さい。
裏紙が残ったまま塗装すると、下記写真のように裏紙の糊が膨れて塗膜を押し上げ、クラック・塗膜剥離を起こします。

*木材・合板はアクが出る上に、塗料の吸込みが大きいため、塗装はお勧めしません。
*じゅらく壁・繊維壁などに塗装する場合は、下地の状態をよく確認して下さい。
剥がれ落ちたり、浮いてボコボコしている場合は、すべて剥がしてから塗装して下さい。
剥がれずしっかり接着している場合は、アク止めを塗布後十分乾燥させてから、しっくのんを塗装して下さい。
*紙クロスや布クロスは吸い込みが非常に大きいので塗装はお勧めしません。
*じゅらく壁・繊維壁などに塗装する場合は、下地の状態をよく確認して下さい。
剥がれ落ちたり、浮いてボコボコしている場合は、すべて剥がしてから塗装して下さい。
剥がれずしっかり接着している場合は、アク止めを塗布後十分乾燥させてから、しっくのんを塗装して下さい。
*紙クロスや布クロスは吸い込みが非常に大きいので塗装はお勧めしません。
注) シーラー処理について
しっくのん及びしっくのんAを塗装する場合、必ず水性カチオンシーラーを塗布してからしっくのんを塗装して下さい。(シーラーを使わず直接しっくのんを塗ると、吸込みムラや塗装ムラになったり、塗膜剥離を起こします。写真参照。)
また、主原料が古来の漆喰と同様消石灰であることにより、特性上乾燥収縮が起きやすくa、ジョイント部やコーナー部に軽微なクラックが入る場合がありますのでご了承下さい。
a しっくのん及びしっくのんAは、塗布後乾燥していくにつれて空気中の二酸化炭素と反応し、原料の石灰石に戻っていく性質があります。

しっくのんの用途
標準使用量は?
標準膜厚
塗装間隔
塗装要領
A10: 「しっくのん」及び「しっくのんA」は、普通の合成樹脂エマルジョンペイントとは異なり、消石灰などの粒子が主原料です。このため、塗膜の重なり部分がムラとなりやすく、塗膜が多孔質になるため吸水性が大きく、塗り重ねる場合は塗りにくくなります。
以下留意点として、
1.塗り伸ばし
ローラーに塗料を十分含ませて塗り伸ばしますが、力を入れて搾り出すような伸ばし方は避けて、
軽く無理なく伸ばせる程度で止めて下さい。塗りムラの原因となります。
2.同一面の塗装
区画された同一面は休まずに塗装して下さい。途切れるとその部分が塗膜厚さのムラになります。
3.水による希釈
原則無希釈で使用します。但し、気象条件等で塗りにくい場合には、1~2%の水で希釈して下さい。
希釈しすぎると下地の隠蔽性が低下したり、色ムラ・塗膜剥離の原因となりますので注意してください。
また、希釈後は中身が均一になるようしっかり攪拌して下さい。
4.一旦下地が透けて色が出る(色の上りが遅い)
塗装前は少し濃い色をしていますが、塗装すると一旦下地が透けてまだら模様のように見えます。
乾燥するにつれて少しずつ色が出てきて所定の色になります。ご留意下さい。
5.撹拌
缶の蓋を開けたら原料が分離していたり、粘度が高くなっている場合があります。
撹拌機で中身が均一になるよう十分撹拌をして下さい。
棒切れでも大丈夫ですが、最低でも2~3分以上はかき混ぜて下さい。
缶を抱えて振るだけですと中身は十分に撹拌されません。
撹拌が不十分な場合、色ムラや塗膜剥離の原因となります。
*しっくのんは空気中の二酸化炭素を吸収して硬化しますので、塗料をバケットに移したらすぐに蓋を閉めて下
さい。
塗装を一時中断する際は、バケットに塗料が残っていたら、ラップかビニール付きのマスキングテープでバケ
ットを覆って、空気に触れさせないようにして下さい。
養生テープを剥がす時はテープに付着した(硬化した)塗料がパラパラと落ちてきますのでご注意下さい。
*しっくのんは消石灰、炭酸カルシウム、還元澱粉糖化物などの自然素材を原料としており、下地の状態や塗り
方、気象条件などによっては、ローラーの筋ムラが見えたり、ジョイント部にクラックが発生する場合があり
ます。ご了承下さい。
*白華(白化)現象について
しっくのんの塗膜に触れると白い粉が付くことがあります。
これは漆喰の「白(はっ)華(か)」という現象で、漆喰の乾燥途中に水分が蒸発しきれずにずっと残り、
水に溶けた石灰分が表面に出てきた現象です。冬場や梅雨時に起きやすく、乾燥不良が主な要因です。
*気象条件
① 炎天下での施工は、塗装ムラの原因となりますので避けて下さい。
② 夜間気温が0℃以下になることが予想される場合は、できるだけ日中の早い時期に施工を終了させ、乾燥時
間が取れるようにして下さい。
また、気温が5℃以下での施工はお勧めしません。乾燥の遅れによる色ムラや白華の恐れがあります。
湿度が高い日の施工もお勧めしません。
特に入隅など空気の流れが悪い場所は乾燥が遅れてシミのようになる場合があります。
③ 気温15~30℃、湿度40~65%が最適です。
④ 施工時、施工後は換気を促して下さい。(ただし、ドライヤーなどで強制乾燥することは避けて下さい。急
激な乾燥により表面にクラックが起きる場合があります。)
しっくのんは自然素材で出来ておりますので、下地の状態が良くないと仕上がりに影響が出ます。
以下の点には特に留意して下さい。
・しっくのんは塗装後二酸化炭素と反応して硬化しますので、躯体のちょっとした動きでクラックが入る場合が
あります。
・蓋を開けたら十分に攪拌して下さい。不十分なまま塗装をすると、成分が下に沈殿したままとなり、上澄み液
を塗ってしまい、結果塗膜が剥がれる場合があります。
・下塗りの水性シーラー・プライマーはメーカーが記載している乾燥時間より長く取って下さい。乾燥不足のま
ましっくのんを塗ると、黒ずんだシミが残ったり、接着不良により塗膜が剥がれることがあります。
・冬場と梅雨時は特に施工に注意して下さい。冬は5℃以下での施工は避けて下さい。梅雨時に湿気が極端に
高い時は施工しないで下さい。いずれも乾燥が遅れて湿ったようなシミになります(特に空気の流れの悪い
入隅など)。
・既存の壁(クロスやじゅらく壁など)に塗る場合は、下地の状態を良く確認して下さい。手で触ると下地がポ
ロポロ剥がれ落ちたり、あるいは剥がれている場合は、パテ等で補修をするかすべて剥がしてから施工して下
さい。
免責事項
しっくのんは無機素材です。
しっくのんは無機素材です。
塗装後二酸化炭素を吸収して元々の石灰石に戻る働きがあり弾力性に欠けるため、下地が動いた場合ジョイン
ト部にクラックが生じる場合があります。
また、原料の特性上、下地の状態、塗り方・乾燥の速度、気象条件、光の当たり具合によっては、塗膜の重な
り部分が筋のように見えたり、色ムラが生じる場合もあります。
これらの事をご理解いただいた上でお使いいただきますようお願い申し上げます。
また、当社では施工方法の不具合による責任は負いかねますので、ご了承下さい。
これらの事をご理解いただいた上でお使いいただきますようお願い申し上げます。
また、当社では施工方法の不具合による責任は負いかねますので、ご了承下さい。




